
イラストレーション:火取ユーゴ
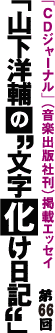
伝月統日 京都で笛の藤舎名生さんのリサイタルの助っ人。フリープレイのデュオで一曲参加する。終演後、楽屋に芸妓さんたちがやって来るというのが名生世界か。名前を書いた千社札をいただいて喜ぶ。名生先生のお父さんが亡くなられた時には葬儀に芸者さんが200人並んだそうだ。いやあ芸事や伝統というものは贅沢なんですね。
2月26日 恒例の226コンサート。リーダーの早坂沙知(as,ss)と、つの犬(ds)が同じ日の生まれだ。助っ人は永田利樹(b)、コスマス・カピッツァ(per)、大儀見元(per)。サッちゃんは肺に水がたまるという病気の最中に、病院から抜け出しての熱演。看護婦さん達が来ているので安心というが大変な筈だ。おれも昔、肺に水がたまって長期間戦線離脱した。肺炎になっているのに休まずにアバレているとこうなる。同じ誕生日だと同じ病気になるという一例にはなるが、つの犬にはくれぐれも気をつけてもらいたい。ゲストにカルメン・マキ(vo)という豪華な早坂コネクション。打ち上げには沖山秀子さんが残ってくれていて、故今村昌平監督の話をしたりする。なんか濃いメンツの打ち上げでした。
年月金日 というわけで年金年齢になったので、届いていた書類を持って役所に行って全部手続きをする。40年前にバンドマンに嫁ぐ娘に、とにかく夫婦で国民年金には入っておきなさいと言った義母の言葉が今生きた。
晋月平日 作曲家中山晋平の生誕120周年記念の映画を作っている人達がいて、インタビューをされる。自分の演奏に日本のメロディーをいくつか取り上げているが、中山晋平作品が圧倒的に多いのだ。「砂山」「うさぎのダンス」「あの町この町」「雨ふりお月さん」「シャボン玉」など。20年前にも晋平特集のテレビ番組があって「あの町この町」を弾いて話をしている自分の姿をNHKアーカイブスで見た。「ラベルの『ボレロ』やガーシュインの『ラプソディ・イン・ブルー』と同じで、自分の即興演奏の素材になると感じる素晴らしい曲として接している」という意味のことを画面で言っていたが、それは今も変わらない。ところで、中山晋平の活動期、そのピアノ伴奏で踊った革新的な日本舞踊家、藤蔭静枝という人がいる。この二代目の方が京都にいて、これまた2000年にニューヨーク・トリオと共演をしたということがあった。その話もする。資料によると初代の藤蔭師匠はパリから晋平さんに電報を打って送金を頼んでいる。面白い時代だったんですね。
ジャ月ズ日 恒例の函館山のクレモナ・ホールでのソロ・コンサートは、くっきり晴れた、あの函館の夜景をバックにやることができた。帰ってきて鎌倉でスペシャル・ビッグ・バンドの再演。リズム・セクションに金子健(b)、高橋信之介(ds)、ゲスト歌手がケイコ・リーというリニューアル版だ。終演後楽屋に玉木正之さんが乙武洋匡さんや澁澤龍彦夫人を連れて来てくれる。「おふくろさん」騒動の話題になり、ジャズの曲でそういうことを言い出されると大変だが、クラシックではそういう問題はどうかと聞くと、「そういえばベートーヴェンの第九がそうだ!」とのお言葉。シラーの詞の前にベートーヴェンは自分で勝手に別の詞をつけ加えている。当時シラーは既に亡くなっていて遺族からも文句は出なかったので、あの名作がこの世に残っていたのだった。このスペシャル・ビッグ・バンドの選抜メンバー松本治(tb)、川嶋哲郎(ts, ss)、池田篤(as)と前述のリズム・セクションで、渋谷のJZ ブラット、京都のRAG、岩国のシンフォニア岩国と渡り歩く。岩国公演後、宿泊場所の広島に取って返し、すぐにお好み村へ。有名な「八戒」が予約できていた。極上の味を満喫。以前にここに来たウイーン・フィルやモンテカルロ・バレエ団の人たちの行状をご主人から聞いて笑い転げる。色紙に「ジャズ参上」と書いて皆で寄せ書きをする。手伝いの可愛い小学生は、娘のアヤカちゃん。帰り際に「このままおじちゃん達について来て歌ったり踊ったりする?」と聞くと、きっぱり首を横に振られた。翌日、全員お好み臭が服から抜けない。プロデューサーの東福寺女史が「ホテルの部屋に消臭剤の瓶があったのはこの為だったのだ!」と気づき、一同、広島文化の深さと連携はさすがと納得したのだった。
「CDジャーナル」2007.5月号掲載